地域包括ケアシステムと在宅医療の看護師の役割とは?
地域包括ケアシステムの現状と地域の看護師の仕事・役割をまとめました。
地域包括ケアシステムと看護師
厚生労働省は、2025年に団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)になり、重度な介護が必要になっても住み慣れた地域で自立して快適に暮らせるように体制を整えています。
それが医療、介護、住まい、介護予防・生活支援を確保し、それぞれが連携する「地域包括ケアシステム」の構築です。
地域包括ケアシステムでは、保険者である都道府県、市町村が地域の特性に応じて、医療、介護に関するさまざまな職種のスタッフの連携により、サービスを提供します。
たとえば、地域医療を担う主治医(かかりつけ医)やケアマネジャー、地域包括支援センターなどが利用者の医療、介護の相談にのり、医療から介護または介護から医療の円滑な移行を促進します。
看護師のニーズも介護施設、地域包括ケア病棟・回復期病棟、訪問看護ステーション等で増えており、地域包括システムに関わる看護師求人サイトの求人案件も増加しています。
地域包括ケアシステムを簡単に説明すると



したがって、現在(2018年)の病院、介護施設の支援体制では、立ち行かなくなるため、医療、介護、予防と住まい、生活支援・福祉サービスを支援する体制が必要になります。
それが高齢者の在宅生活を支える制度、「地域包括ケアシステム」なのです。
以下、厚生労働省の地域包括ケアシステムの取り組みをご覧ください。
地域包括ケアシステム実現に向けての5つの取り組み
①医療、訪問看護、介護、リハビリテーションの連携を強化する
②介護サービスの充実させ強化する
③要介護状態とならないための予防を促進する
④見守り、配食、買い物など多様な生活支援サービスを確保する
⑤高齢者になっても住み続けられる高齢者住まいを整備する

看護師も地域包括ケアシステムの中での役割があるってことですね。

看護師の役割として、地域に住んでいる人の暮らしをいかに支えていくか、そのために他の職種との連携し、迅速かつ丁寧な対応をする必要あります。
高度急性期の病棟看護師から在宅医療・介護の訪問看護師まで多かれ少なかれ関わりがありますので、普段から地域包括ケアシステムの情報・ニュースを集めて来るべき時に備えておくとよいでしょう。

地域包括支援センターの役割とは?
地域包括支援センターは地域包括ケアシステムの中心的な存在です。
地域包括支援センターは市町村が主体となり設置され、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーを中心としたチームで、高齢者の支援にあたっています。(介護保険法第115条の46第1項)
現在、地位包括支援センターは4,328ヶ所あります。
地域包括ケア支援センターは、その地域の住民、民生委員、警察、消防署、医療機関、民間企業と協力体制をとって、高齢者を見守るネットワーク作りを進めています。
そのネットワークにより、高齢者の介護や健康、権利、その他の問題を発見し、地域包括ケアセンターに報告します。
報告を受けた地域包括ケア支援センターは適切な機関と連絡を取り、問題を解決すべく高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指すのです。
在宅医療・介護と病院・診療所の役割とは?
地域包括ケアシステムにおいて、在宅の患者は介護福祉サービスとして、訪問看護・デイサービス、診療所・クリニックなどの訪問診療・往診、訪問看護ステーションから訪問看護、調剤薬局から服薬指導などを受けることになります。
定期的に患者の自宅を訪問し、通院できない患者の要請に応えたり、容体が急変したときに24時間体制で治療を行えるようになりました。
現在、24時間対応できる在宅療養支援診療所は、全国で1万5千件近くあります。
高齢者を中心に末期がん患者、慢性疾患を抱える患者が在宅医療を受けています。
在宅医療を受けるには、訪問看護師の看護ケア、理学療法士・作業療法士によるリハビリテーション、そしてケアマネジャーによるケアプランの作成など連携、関わりが必要です。
在宅医療の中で病院は入院から退院後の治療計画について話し合い、また患者の急変時に重要な役割を担うことになります。
訪問看護師に期待される役割と機能とは?
地域包括ケアシステムでは、訪問看護師の役割も期待されています。
訪問看護ステーションには、看護職員が2.5人以上勤務する従来の訪問看護ステーションと看護職員が5~7人以上勤務し、24時間対応、看取りサポートを積極敵に行う機能強化型訪問看護ステーションがあります。
今後の訪問看護に期待されるのは、24時間対応、重度化対応、訪問回数を増やすことのほかに看取り機能の強化も大切です。
厚生労働省によると、現在病院で最期をむかえる人が約80%にのぼりますが、訪問看護の利用者については約56%が在宅死されています。
地域包括ケアシステムの中での訪問看護の大切な役割は、住み慣れた地域での在宅療養を最後まで支えていくことです。
今後、2025年に向けて訪問看護師のニーズが高まることは間違いありません。
総合病院から訪問看護師に転職(体験談)
新人1年目の頃は毎日のように先輩に怒られ、辛い日々でした。
しかし努力の結果、2年目からは仕事を覚え、準備などを事前にして、スムーズにできるようになりました。先輩から怒られる事もなくなり、看護師として充実していました。
しかし、今度は夜勤やチームでの連携が大変に感じるようになりました。
忙しいすぎる上、人間関係にも疲れていました。
そこで転職を考えました。
色々と調べ、訪問看護の仕事に興味が湧きました。
私は病院での人間関係に疲れていたので、訪問介護だと個人で動けるという事が魅力的でした。
病院やクリニックで働く看護師は絶対にチームや誰かとの連携が必要ですから、医師の指示や看護師長の命令、私のミスが全体のミスになる、というストレスから解放されたかったです。
訪問介護を利用する方はお年寄りが多いので、おばあちゃん子だった私にはそれもポイントでした。
そして、転職を決意しました。
訪問看護の仕事は、慣れれば1人で動くことができます。朝に訪問看護ステーションに出勤して、タイムカードを押したら自家用車で訪問介護をします。
診療所や介護との連携が欠かせませんが、個人で動けるという事は自由度が高く、プレッシャーがなくなりました。
医師との細かな連絡で指示を守り、独断での判断は避け、色々と気をつける事はありますが、大変な仕事上の人間関係がなくなり、快適になりました。
あのまま総合病院勤務を続けていたらストレスで体を壊していたかも知れません。
今はよく知っている地域の訪問介護の仕事で充実した日々を過ごせています。
急性期病院外科病棟から地域包括支援センターに転職
(20代前半・女性)
年収は2年目で410万でした。二交代勤務です。
祖母の入院がキッカケです。
脳梗塞で嚥下障害とADL低下となり、慢性期の病院に入院していました。
看護師の積極的な看護介入、特に口腔ケアの充実に大変感動しました。
お陰で亡くなるまで祖母は自分の歯を健康に保つことが出来ていました。
国立大医学部に入学し、まずは急性期で経験を積もうと考えて就職を決めました。
転職回数は1回。来年度から地域包括支援センターに転職することになりました。
急性期で技術的な経験は積むことができるものの、退院後の生活のイメージがつかず、退院支援において自分が計画し、看護介入していることが正しいのか、自宅や転院先等で生かすことができるのかわからなくなりました。
大学時代から在宅看護に興味があったのがキッカケで、地域の中での看護師の働き方や必要性を学ぶ研修を受けることができ、今回の転職もその研修での人脈で決定することができました。
病院にいるとどうしても、看護師は病院ファーストであるという考えに至りやすいのではないかと思います。
技術や知識は確かに必要だと思います。
入院患者の殆どは自宅に帰りたいと希望されているのですが、家庭環境や住環境によって自宅では過ごせない方を沢山みてきました。
住み慣れた地で生き生きとその人らしく過ごすことができるよう、看護的介入していけるような看護師、看護師らしくない看護師を目指したいです。
面接は紹介だったこともあり顔パスでした。
興味のある研修に参加してそこからの繋がりで転職も可能であることもわかりました。
顔が見えているから安心でした。
まずは現在の環境で目標としていることが出来そうなのかというアセスメントが必要だと思います。
できるのならその場にいた方がいいと思います。
転職は手続き等色々と面倒です。笑
ただ、無理をしてその場で働き続けることはしなくていいと思います。
引く手数多な職ですし、探せば自分に合った環境は見つかります。自分を大事に。
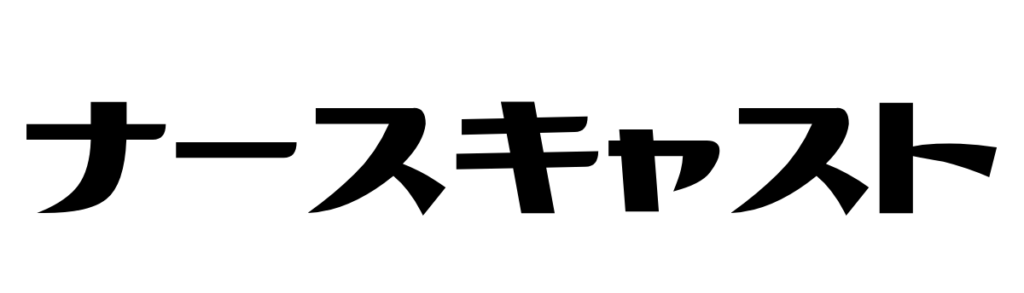
















母娘で看護師をしております。
私は総合病院で勤務していますが、
母は介護施設のデイサービス等で働いています。
総合病院の様な夜勤等はなくシフト性で自分のスタイルで働けているようです。
母の年齢になっても看護師の需要は高く、
高齢化社会になった今は介護施設等での募集がとても多いですね。
現在の職場を退職する時にはそちらの方面への転職も視野にいれております。