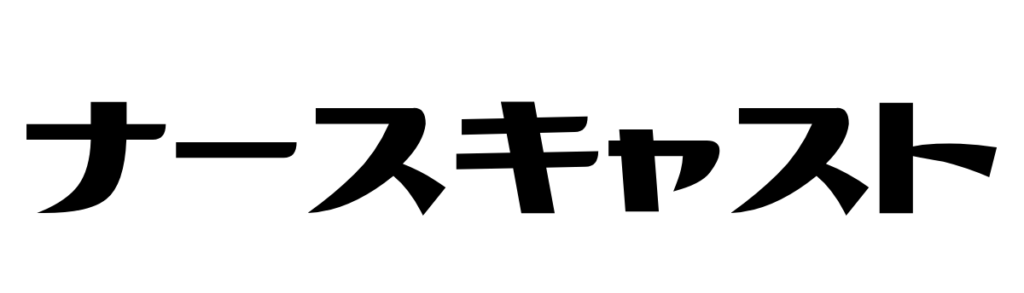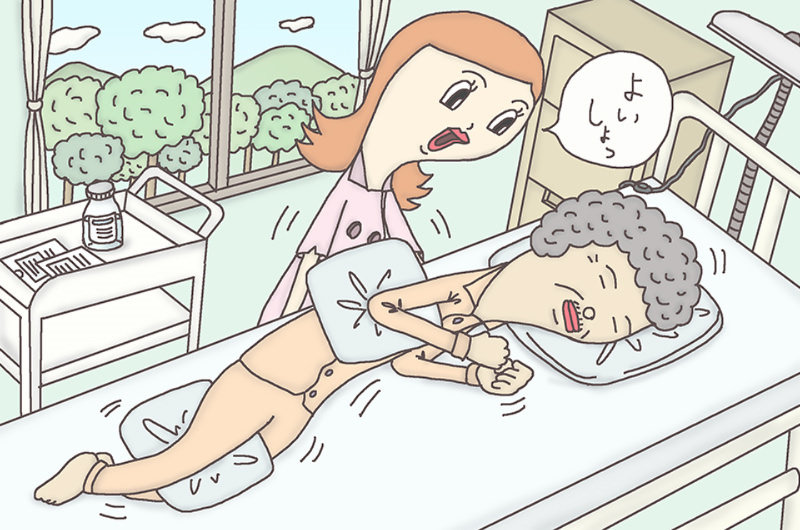看護師のおすすめ本は?看護師さん33人に聞いた転職先でも役立つナースの仕事本
看護師に関する本でおすすめは?口コミで評判、転職先でも役立つナースの仕事本の口コミ・評価・レビューのまとめ(WEB調査期間:2019年02月18日~2019年03月4日)。



その他にも様々なナースの本が支持されていますが、良書が多いですね。
看護師のオススメする本一覧
- 最後の医者は桜を見上げて君を想う[TO文庫・二宮敦人(著)、syo5 (イラスト) ]
- ICU3年目ナースのノート[道又 元裕(総監修) 露木 菜緒(監修・解説)]
- 病気がみえる(シリーズ)[医療情報科学研究所]
- からだがみえる(シリーズ)[医療情報科学研究所]
- ねじ子のヒミツ手技[森皆 ねじ子(著)]
- 世界一やさしい解剖・生理学[中田 圭祐(著)]
- 看護雑誌「エキスパートナース」[照林社]
- がんばらない[鎌田 實(著)]
- たった20項目で学べる褥瘡ケア[安部 正敏(著)]
- ワークシートで指導と評価がラクラクできる!臨地実習指導サポートブック[足立はるゑ(著)]
- おたんこナース(漫画)[佐々木 倫子(著)]
- 妊産婦と赤ちゃんケア[日総研出版]
- 看護に活かせる心電図ノート[鈴木まどか(著)]
- 実践的看護マニュアル[川島 みどり(編集)]
- 看護の現場ですぐに役立つモニター心電図[佐藤 弘明(著)]
- ねじ子のぐっとくる脳と神経のみかた[森皆 ねじ子(著)]
- 全部見える 整形外科疾患[高井 信朗 (監修)]
- かんたんポイント心電図 第2版 これならわかる![奥出 潤(著)]
- オールカラーまるごと図解 ケアにつながる脳の見かた[波多野 武人(著)]
- ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術[中山 有香里(著)]




主人公(筆者)が新人の看護師としていのちに向き合う姿が心に響く本だと思います。




・看護師の転職で役に立ったおすすめの本は?ナースの転職必勝マニュアル
看護師さん33人に聞いた転職後も役立つナースの仕事本の口コミ・レビュー
(※看護師におすすめの本、仕事に役立った本を10点満点で評価していただいていますが、あくまでも個人的な感覚で評価していただいている点数なので参考程度にしてください。)
インターネット調査により、看護師さんの仕事に役立つ本、お勧めの本について聞きました。
■病気がみえる本シリーズの口コミ・評価・レビュー(6票)
看護職なら必ず一度は目を通しておきたい本ですね。

【9/10点】
病院で行われる入院から検査、治療法の一連の流れが分かる本
(Sさん/兵庫県/20代後半/女性)
在宅で看護職をしています。雇用形態はパートです。年収は108万未満です。
家庭優先で週に1、2回在宅看護の仕事をしています。
在宅看護は産後仕事復帰という形でしています。出産する前は病院の内科病棟で働いていました。
今回私がおすすめする書籍は「病気がみえる」シリーズ本です。
病気がみえる本シリーズは循環器や呼吸器、免疫など、それぞれの分野の疾患が詳しく載っています。
私はこの本の循環器を学生の頃に購入し実習でも参考にしていました。
疾患について解剖学的にどうなっているのか、そのためどのような症状がでるのか、主に行われる検査や治療法はなにかといったように病態、症状、検査、治療法が流れに沿って書かれています。
そのため病院で行われる入院から検査、治療法の一連の流れを想像しやすくなると思います。
「病気がみえる」シリーズは大きく病態から治療法までの全体像を説明しているので、解剖学、検査治療法のやり方は自分でほかの書籍を参考に調べればもっと理解が深まると思います。
そのためにこの「病気がみえる」シリーズはとても役にたつ書籍だと思います。
【8/10点】
見やすいのでおすすめ
(Yさん/和歌山県/20代前半/女性)
急性期病棟で働く20代前半女性で、看護師歴3年目になります。診療科は呼吸器・内科・胸部外科の混合病棟です。
転職経験はなく、3年間同じ病棟で働いています。
看護学生時代から「病気がみえるシリーズ」にはお世話になっており、看護師として働きはじめてからもすごく役にたっています。
中身がカラーで、写真も多く使用されているため見やすいところが一番この本が好きな理由です。
写真が多く載っているため、言葉だけではイメージしにくいものも写真を見ると「あっこんなのなんだ。」と頭に入ってきやすいです。
また、疾患ごとの項目にわかれており、その疾患の病態・治療方法・検査内容などが小項目にわかれ記載されているのでパッとみるだけで大まかにその疾患の全体像を把握することが出来ます。
そのためあまりいらっしゃらない疾患の患者さまが入院してこられたときにはサッと本を開き勉強することもあります。
様々なシリーズがでているので、部署移動があった際にはその部署に合った「シリーズ」を購入したいと思います。
【9/10点】
看護学生にもおすすめしたい一冊
(Hさん/山口県/30代前半/男性)
私は、准看護師学校を経て専門課程(看護師)の学校を卒業しました、その間は高齢者を対象とした病院で働きながら学校へと通っていました。
その在学中に、とても役に立った(看護師生命を救われた)のがこの『病気がみえる』のシリーズの本でした。
この本は、循環器、消化器、運動器など他臓器ごとに分厚い本がシリーズ化されており、no.11まで存在します。
それぞれの臓器の説明はもちろんかなり詳しく載っています。
例えば従来であれば、鉄欠乏によって鉄欠乏性貧血が進行する、といった内容を本書では鉄欠乏により、貯蔵鉄、血清鉄が低下し肝臓へのペプシジン産生が低下し…というように細胞レベルでの解説をしてくれます。
実際の現場ではそこまで質問されることもなく、Drレベルの項目となるのですが、看護師として基礎的な知識を学ぶ際にはそこまで求められることがあり、そんな時に本当に役に立ちました、
また、図解してわかりやすく書いていることもすごくイメージしやすく読みやすい本で他の看護学生にも強くお勧めしたい一冊になっています。
【9/10点】
ドクターも認めている本
(Mさん/静岡県/30代前半/男性)
わたしは産婦人科クリニックにパートで勤務している看護師です。
子どもが小さいため日勤のみのパートをしており、年収は250万ほどです。
今までは消化器内科外科・脳神経外科・血液内科・婦人科に勤務の経験があり、出産を機にパートでの勤務をはじめ、昨年第一子が小学生になったため、産婦人科のクリニックに転職しました。
産婦人科は初めてだったので、早く慣れたいという気持ちが強かったので、病気が見える産婦人科の本を買って、何度も読み返して勉強しました。
イラストと一緒に丁寧に説明や文章が記載されているので覚えやすく、初心者のわたしにはとてもわかりやすかったです。
婦人科はすでに持っていたので読み返しておさらいしました。
やはりわかりやすく、病院にも病気が見えるが置いてあり、先輩方も本を読んで勉強されているのを見ると、どの世代の方にも信頼されており、ドクターも認めている本なのだと思います!
全ての科の本が揃っているので、自分の所属された科の病気が見えるを購入して、しっかりと勉強されることをオススメします!
【10/10点】
自分の勤務している科のシリーズだけでもおすすめ
(Mさん/愛知県/30代前半/女性)
私は10年目の看護師で、今までに内科、手術室、外来、救急などで働いていました。
今は総合病院を辞めて、個人病院のペインクリニックで働いています。
日勤だけの勤務なので体は楽ですが、子育てをしながら日々奮闘しています。
病気が見えるという本はシリーズになっていて、それぞれ循環器や消化器など科別に分かれています。
病気について調べる時に、とてもわかりやすく説明が書いてある事と、カラーの絵で見やすいです。
観察項目や注意点もわかるように書いてあります。
国家試験の勉強をする時にも重宝しました。
少し大きくて重いので持ち運びには不便ですが、大きいので見やすく調べ物をする時には使えます。
値段も一冊3000円程度なのでシリーズで全て集めたら結構なお値段になりますが、自分の勤務している科のシリーズだけ購入してみても良いと思います。
とても勉強になるので、書店で見かけたらページをめくってみてください。
きっと、気にいると思います。
【9/10点】
「病気がみえる」シリーズの呼吸器がおすすめ
(Kさん/静岡県/50代後半/女性)
現在は、非常勤講師の仕事をしていますが、それ以前は大学の看護学の教員をしていました。
臨床は外科系、急性期の病棟や集中治療室での看護師の経験があります。
大学では成人看護学の授業を担当していましたが、成人看護学の授業では、解剖生理学や疾病治療学の知識を持っていることが前提となっています。
ところが、その知識の定着が必ずしも良くないのが実態です。
この「病気がみえる」は、シリーズになっています。
私は成人看護学が専門ですので、どうしてもお勧めする本は、成人に関連のある本になります。なかでも、新しく改定された、「病気がみえる」シリーズの呼吸器は、内容も充実しています。
基本的な解剖生理学に関する知識から、最新の疾病治療に関する知識まで一冊で網羅できます。
もちろん、本というよりも参考書かもしれませんが、なかにはコラムも入っていて、読み物として最初から読破すると、呼吸器に関する知識が整理でき、大変ためになります。
もちろん、この本は看護師向けだけにかかれたものではないので、看護に関する知識は全くと言っていいほど入っていませんが、それでも、看護師が看護について学習する前に読んでほしい本の一つです。
■ねじ子のヒミツ手技の口コミ・評価・レビュー(4票)
誰にでもお勧めできるとにかくわかりやすい本です。

【10/10点】
新人、ブランクありの人にもおすすめ
(Oさん/埼玉県/30代後半/女性)
正看護師、常勤、慢性期病棟勤務、年収350万、転職経験なし。
ねじこのヒミツ手技は新人の頃非常に読み込んだ本のひとつです。
採血、点滴などの使い方をイラストでかいてくれているので、とてもわかりやすかったです。
他にはないスピッツのこともかかれてあります。本自体とても薄く小さいので、持ち運びが便利でバックに必ずいれていました。
仕事中もポケットにしのばせて、読んでいました。
作者がイラストも書く医療者なので、出てくる医療具がリアルでした。
それでも非常にポップな絵で、なんだかとても和んだのを覚えています。
ほかにも心電図などの書籍もでていますが、これが新人の頃はとても役立ちました。
プリセプターになっても、新人の看護師にはいつもりおすすめしていた本のひとつです。
職場をはなれて、また戻る時も、感覚を取り戻すために、また同じ本を買ったほどです。
それほどまで、基本的な手技を、きちんと丁寧にかかれてあります。
新人や、ブランクのある人は一冊持っているとかなり役立つ本だと思います。
【9/10点】
新人看護師にもおすすめ
(OTさん/福岡県/30代前半/女性)
正看護師として、九州大学病院で勤務していました。雇用形態は常勤2交代で、血液腫瘍内科で勤務いたしました。
経験1年目~3年目までが年収は380~450万円でした。その後は別の大学病院で看護師として勤務後、ワークライフバランスをとるために退職。
現在は、育児に専念しておりますが、復職希望のため転職活動を行なっています。
ねじこのヒミツ手技をお勧めする理由は、看護師の基本の医行為手技(点滴、骨髄穿刺など)が根拠からわかりやすく記載されているからです。
長々とした文章だけではなく、手技についてはイラストで説明してくれているので、飽きずに読むことが出来ます。
また、この本の作者は医師であるため、看護師が書いた本よりも医行為についての根拠は信頼できます。
看護師著者の本は時折、根拠や数値を経験から書いている本もありますので、基本的に鵜呑みには出来ません。
載せられた項目は基本的な医行為ですが、病院に勤める看護師は一通り目にする医行為なので、実践するときや介助につくときにとても役に立ちます。
新人看護師にお勧め致します。
【8/10点】
医師の立場から看護師に必要な動きが分かる
(Sさん/兵庫県/30代後半/女性)
急性期病院の病棟勤務をしています。診療科は今まで消化器外科・整形・循環器内科の経験があります。
正社員として8年の経験を持ちます。
こちらの本が筆者はドクターをされています。
看護技術の本は一般的に看護師が書いている本が多々あります。
しかし、なにかの処置(気管内挿管・トロッカー挿入・ガーゼ交換・中心静脈ルート挿入・Aライン挿入介助)等医師の介助での技術が看護師には多々あります。
つまり医師の技術をある程度理解し、どのタイミングでどのように動けばいいか、何をだせばいいか、医師が何を考えているのかをある程度把握しておくことが大事です。
ねじこのヒミツ手技をおすすめする点は、医師が何を考えどのような技術を行い、看護師にどのタイミングで何をしてもらいたいか、介助してもらいたいかを書いてくれています。
医師の立場から看護師の動きを書いてくれているので、現場ですぐに利用することができます。
またこの作者は漫画家としても活躍されているので、イラストもとても上手です。
医療現場でよくみる場面をかわいいキャラクターでわかりやすいように書いてくれているのもポイントです。
【6/10点】
言葉よりイラストの人におすすめ
(Mさん/大阪府/40代後半/女性)
40代後半、整形外科での勤務経験あり。 現在は、子育てのため仕事はしていません。
しかし、仕事のことの勉強は常にしておかないといけないと思ってねじ子のヒミツ手技 は読んでいます。
看護本だと、わかりにくいものも多いのでいろんな本を買いました。
他にもいい本はあると思いますが、私にはこの本のほうがわかりやすいです。
文章だけだと分かりにくいところも、イラストなどもおり交ぜながら載っているので、読みやすいです。
文章ばかりでは、読むのも疲れてきたりするので、ほどよくイラスト入りだと読んでいても飽きないし、やり方など絵のほうが分かりやすいです。
手技は、言葉では理解しにくいところがあると思います。
なので、イラストで事細かに書いてくれているので、理解しやすいのかもしれません。
私みたいに言葉よりも、イラストなど好きな方にはオススメ出来ると思います。
どんな本もですが、理解出来ないと読んでいるのも嫌になってくるので、自分にあったものを探すのが一番いいと思います。
【8/10点】
イラストが可愛く頭に入りやすい
(Mさん/三重県/20代後半/女性)
看護師として働いて5年目となります。新卒で総合病院で働き、現在は介護施設にて勤めております。
病院では内科、脳神経内科、整形外科、泌尿器科などで勤務経験があります。
病院勤務時代の年収は交代勤務をして400万円程です。現在は介護施設で年収350万円程です。
介護施設では病院とは違う部分がたくさんあり、戸惑うこともありますが勉強の日々です。
疾患のことや、解剖生理を勉強し直すことも多々あります。学生の頃からねじ子シリーズにはお世話になっていました。
イラストが可愛く、見やすいのでとても好きです。勉強のやる気があるときはもちろんですが、やる気がなかなかでないときにもイラストで解説してくれてあるので頭に入りやすいです。
脳神経は複雑で難しいイメージがありますが、この本のおかげで脳神経が少し好きになりました。
脳神経系に苦手意識のある方はこの本から入ると良いのではないかと思います。現役看護師や学生の方にもおすすめです。
■ICU3年目ナースのノート(2票)
ICUなら必見!
【9/10点】
ICU看護に必要な知識が細かく載っている
(Aさん【執筆者の1人】/茨城県/30代前半/女性)
看護師11年目、現在は育児のため離職中です。
都内の看護学校を卒業後、付属の大学病院のICUで6年間働いたのちに結婚・夫の海外転勤を機に退職しました。
帰国後、夫の赴任地の救急指定病院ICUに転職しました。
家庭の事情により、夜勤ができなかったので非常勤の日勤フルタイムで働いていました。
1人目を出産後、保育園が見つからず退職し、そのまま2人も出産し、現在に至ります。
この本をおすすめする理由は、ICU看護に必要な知識が細かく載っていること、執筆にあたり認定看護師が指導しているため内容に正確性があることです。(初版は私も執筆していました。)
細かく書いてありますが、内容理解もしやすいように書かれていると思います。
疾患・術後管理については解剖生理も載っているため、基礎的な解剖生理を復習することもできます。
また、使われている図もわかりやすいと思います。
病院によって、術後管理や推奨している看護技術などは異なってくるとは思いますが、基本的なところは書かれていると思います。
【8/10点】
ベテランナースに負けない知識を積めるのでおすすめ
(Sさん/山形県/30代前半/女性)
大学病院のICUで約5年働いた経験のある看護師です。
私が勤務していたICUは3交代と2交代の両方ともあり、基本的には1~2:1の受け持ち体制でした。
入室する患者は5割が心臓血管外科、2割が呼吸器外科、残り3割が一般外科(消化器全般、耳鼻科、口腔外科、小児外科、形成外科など)といった割合です。
臓器移植や人工心臓なども取り扱う病院だったため、近隣の県からも様々な疾患の患者が集まってきました。
ME機器も頻繁に更新され、補助循環や透析、人口呼吸器など、覚えなければならない機器類も非常に多かったです。
「ICU3年目ナースのノート」には、ICUに入院する患者を看護する上で必要な基礎知識がぎっしり、しかしコンパクトに詰まっています。
ICUに異動してきたばかりの頃は本当に助けられました。
教科書や参考書では今ひとつ実践的でない情報しか載っていなかったり、臨床にそぐわない内容だったりするのですが、この本はすぐに使える情報ばかり載っています。
クリティカルケアを行う上で基本的な循環動態のベーシックな知識から復習できます。
毎日使う血液ガス分析の結果からのアセスメントの仕方、ME機器の仕組み、それが作用する機序まで、かゆいところに手が届くといった内容がてんこ盛りです。
特に補助循環の仕組みなどは教科書や参考書ではなかなか分かりやすい解説がなかったりするところ、この本は本当に分かりやすく、各種機器が載っているので便利です。
これ1冊を熟読するだけでも、ベテランナースに負けない知識を積むことができます。
■おたんこナース(漫画)(2票)
看護師の漫画の中でも人気が高い名作。

【10/10点】
「生きる」意欲を与えてくれる漫画
(Aさん/東京都/20代前半/女性)
専門学校卒業後、正看護師として総合病院へ就職。腎臓・糖尿病内科に配属。正社員として働き5年目。年収は500万程度。
去年の4月から夜勤専門として働いています。転職経験はありません。
4月から夜勤専門として働いているので、月に夜勤が8~9回程度。日勤は0回です。
病棟の人員不足のため、辞めれずにいます。
今は夜勤専門もしながら毎月少しずつ有給消化しつつ、次に働きたい看護の道を探しています。
初めは、夜勤ばかりの生活に慣れずに心身共に疲れきっていましたが、3ヶ月程すれば上手くバランスをとれるようになってきました。
新しい看護の道を探す材料としてたくさん本を読むようにしています。
看護師を辞めたいなと思った時に出会ったのが、昔から有名な「おたんこナース」という漫画です。
一度読んだら何度も読み直したくなる漫画となりました。それは、なんといっても主人公の看護師の愛すべきキャラ。
ただただほっこりする話ばかりではなく、ほろ苦いさもありつつ心温まる笑いがちりばめられたストーリーが気に入っています。
そして、やはり何といっても絵が繊細で医療機器がとても細かく描かれています。
それぞれ多彩で現代的な内容のテーマになっているのも魅力的です。
本巻には、認知症や末期癌の患者との心の通い合いを描いた物語があります。
患者も主人公の看護師も、互いに弱みをもちながらも共に「生きる」意欲を与えてくれます。
昔の漫画なので現代と違うことも多いですが、総合病院の看護師の苦労はそれほど変わっていないと感じます。
もしかしたら、現代の方がクレーマーな患者が増えた分もっとひどくなっているのではないかと実感しました。
是非、看護学生や新人看護師に読んで欲しい一冊です。
【8/10点】
新人看護師にお勧めの漫画
(Dさん/沖縄県/30代前半/女性)
看護師10年目のものです。総合病院の集中治療室に常勤として勤務しています。
年収は430万ほどで転職の経験はありません。
私がオススメする看護師向けの書籍は、「おたんこナース」という漫画です。
少し、古めの漫画なのですが主人公のナースが日々の業務の中での失敗などをユーモアを交えながら描かれているところが特徴です。
特に読んでほしいのは新人看護師です。
なぜかというと、先ほども少しお話しした通り主人公が、失敗をするシーンが多いのですがそこでの対処法を先輩との関わり方も交えながらストーリーが進んでいるからです。
新人や2年目という時期は、失敗がトラウマになったりうまく対処できない時期でもあります。
また、そこでしっかりフォローしてくれる先輩がいるのなら良いのですがそうばかりとは限りません。
そういう場合どうしたらいいのか悩むと思います。
最悪、現場から離れてしまうという人も少なくありません。
看護師の楽しさがわかってくるのは5年目を過ぎたあたりから。
そこに至るまで、もちろん失敗もします。
そのときどうすればいいのかを学ぶことができ、読みおわった後には少し心が軽くなっていることを実感すると思います。

■最後の医者は桜を見上げて君を想う(1票)
【10/10点】
生とは何かを考えさせてくれる小説
(Kさん/大阪府/20代後半/女性)
病棟看護師7年目になり、正社員 500万ほどの所得であり、消化器内科勤務 夫婦共働き、子供なし 転職経験はなしです。
この書籍は、小説です。
タイトルの通り、医療系の小説となります。
とある病院が舞台となり、ひとりの患者に焦点を当てて、その患者の生き様を通して生死感を考えさせられる作品となっています。
とある医師二人が主となります。
ひとりはどのような状況でも奇跡を信じて生きるための医療を考え貫き通そうと努力して患者を励まそうとする医師。
もうひとりは死を選ぶこともまたひとりの人間として正しいと諭す医師。
正反対ながら、どちらも人の生死に真っ向から向き合っている。
そして、どちらも間違いではないけれど選ぶことは難しい。
そんななかで患者が選択し、どうなっていくのか。どのように考えて、どのように生きたのかを描いています。
ひとりの人間として、そして医療に携わる人間として、生とはなにかを改めて考えさせてくれる作品なのでオススメです。
■世界一やさしい解剖・生理学(1票)
【8/10点】
解剖生理の基礎が学べる本
(Mさん/福島県/40代前半/女性)
私は看護師歴約15年です。
これまで看護師としての経験はありながら、解剖生理をわかっているか?といわれると少し自信がありません。
また医師が説明をしているのを聞いて、患者ではなく、自分がよくわかって「うんうん」と返事をしてしまうほど。
そのような看護師なので、解剖生理に関してはあまり自信がありませんでした。
そこでもう一度基礎から見直したいなと思ったときに、この本を手に取ったのです。
看護師になって働いているうちに自然と覚えてしまったものもあります。
しかしながら科が異なると全く必要とされる知識とそうでない知識があるので、自分に関係のない知識が薄れていってしまうのです。
そのような情報を、この本から読み取ることができました。
これまでわかっているようでわかっていなかったこと、また頭の中でこことここはこんな関連があったのかと結びつくこともありました。
やはり看護師の経験がある程度長くても解剖生理は基本中の基礎なので、もう一度見直すことが大切だと思わせてくれた1冊です。
■がんばらない(1票)
【10/10点】
諏訪中央病院の患者さんに寄り添う医療・看護
(Aさん/静岡県/30代前半/女性)
3児の子育てに奮闘中の看護師です。
これまで総合病院、クリニック、健診センターで勤務したことがあります。
今は子育てのため離職中ですが、クリニックのパート勤務で復帰したいと思っています。
私がお勧めする書籍は、鎌田實先生の「がんばらない」です。
これは、私が看護学生時代に読んだ本ですが、その時にとても感銘を受けた本です。
医療者はこうでなくてはならないと思えた本です。
もうすでに頑張っている患者さんに対して、そして患者さんのご家族に対して、医療者としてどう寄り添い、どう接することが大切なのか、鎌田實先生から教えていただいた気がします。
ここの諏訪中央病院の患者さんに寄り添う医療・看護は素晴らしいです。
こうでありたいと思えました。
鎌田實先生の、患者さんの立場に立って寄り添っている姿勢や、いつも患者さん思いで温かく優しい言動、笑顔は患者さんを心から支えていると思います。
私もそんな看護師になれるよう努力したいです。
医療者である人たちにはぜひ一度読んでいただきたいおススメな書籍です。
■たった20項目で学べる褥瘡ケア(1票)
【10/10点】
褥瘡ケアの基本が分かりやすく学べるおすすめの本
(Sさん/東京都/20代後半/女性)
現在は、介護施設にて勤務していますが、病院の病棟での勤務経験があります(外科、緩和ケア、泌尿器科、療養、混合病棟等)。
以前、病棟の褥瘡ケアを管理していた事もあり、上記の書籍がおススメです。
褥瘡ケアの基本が分かりやすく説明されており、カラーで見やすいです。
著作の安部Drは、セミナー等で講師をされている事もあり、褥瘡ケアの重要なポイントが理解しやすく解説されています。
またこのたった20項目シリーズは、皮膚ケアや外用薬の使い方等のものもあり、合わせて読まれるとより知識が深まると思います。
基本に忠実に、根拠をしっかりとしたケアを再確認されたい方だけでなく、褥瘡ケアが初めての新人看護師の方にも活用出来る1冊です。
また、教育に携わる方も分かりやすい資料作りに使う1冊としても使えると思います。
是非、褥瘡ケアを学びたい!と思っている方は、お手に取って勉強してみて下さい。
もう少し詳しく学びたいという方には、同著作の「スキントラブルケア パーフェクトガイド」もおススメです。
■ワークシートで指導と評価がラクラクできる!臨地実習指導サポートブック(1票)
【10/10点】
看護学生の実習指導で悩んでいる方へオススメ
(Sさん/愛知県/30代前半/女性)
総合病院勤務の看護師です。
診療科は心臓外科・循環器内科の病棟勤務で看護学生の実習指導を専任で担当しています。
転職してから実習指導を担当するようになり、指導歴7年です。
私がこの書籍をお勧めする理由をいくつか挙げさせていただきます。
その前に、私がこの書籍と出会ったきっかけですが、臨地実習指導を初めてすることになった時、新人看護師の指導とはちょっと違った指導になることぐらいは理解していましたが、何から始めていいのか全く分からず、困っていた時にたまたまいつも訪れていた書店で見つけたものでした。
この書籍のお勧めなポイントは、まず実習指導をする時のシチュエーション(看護計画やカンファレンス等)別に学生への接し方や指導のポイントが示されていることです。
看護計画立案から実施等は学校で具体的に(それでも現場に出た時には不十分だと感じるのですが)勉強していますが、カンファレンスや患者さんとの関わり等は実際に現場に自分の患者さんで事例を出して話をしてみたり、現場に出て患者さんと関わることで悩む部分でもあります。
そんな学生を前にすると何から指導をすればいいのか指導者も分からなくなってしまいがちですが、この書籍はそんな場面にも困らないように具体的に場面を挙げられて指導のポイントが書かれているので、私自身非常に役に立ちました。
また、看護教員との関わりなども指導をすすめていく中で困難を感じる点でもありますが、そこについても具体策などが挙げられていたりするので、参考にすることができます。
書籍自体も薄めで軽いので、日々の通勤で持ち歩くには支障はないと感じます。
看護学生の実習指導で悩んでいる方へオススメの1冊です。
■妊産婦と赤ちゃんケア(雑誌)(1票)
【9/10点】
助産師にお勧めの雑誌
(Sさん/青森県/30代前半/女性)
現在は入所定員90名の福祉施設に正看護師として勤務していますが、以前は総合病院で助産師をしていたことがあります。
年収は300万円程度、夫と子供2人の4人暮らしです。
総合病院2箇所、診療所1カ所、現在の職場の転職経験があります。
この雑誌は助産師時代によく読んでいた雑誌です。定期購読していましたが、一般の書店ではほとんど扱っていないようです。
2か月に1回の創刊で、全国の病院で行われている最新の妊産婦ケアが紹介されています。
研究に基づいたケアもあれば、病院独自で試行錯誤しているケアの方法などもあり、とても勉強になりました。
助産師を退職してからも購読していましたが、ある時以前勤めていた病院の記事が載っていたこともありました。
全国各地の取り組みが収録されているので、思わぬ知人に本の中で再会できることもあるかもしれません。
身体の技術的なことや、声のかけ方など精神的なケアまで幅広く扱われています。
雑誌や本を読むときは情報の不確かさなどを気にしたりしますが、日総研は専門分野を扱う会社なので、情報の信憑性などをあまり気にすることなく安心して読むことができました。
■看護の現場ですぐに役立つモニター心電図(1票)
【9/10点】
心電図が苦手の初心者や看護師におすすめ
(Kさん/大阪府/30代後半/女性)
助産師と看護師の経歴があります。常勤の助産師として採用され、総合病院で産婦人科患者様の看護に携わってきました。
その間に二児の母となり、育児休暇取得後は日勤常勤として勤務していました。
その後、夫の転勤についていき、新たな土地で看護師の日勤常勤として採用され、呼吸器・心臓・内分泌内科、整形外科の混合病棟で勤務していました。
看護師の現場で役立つ心電図モニターの本は3年目に購入しました。
私は新人時代から心電図が本当に苦手でした。
産婦人科勤務だったので心臓疾患を抱えている患者様は少なかったのですが、化学療法中に心毒性のある薬剤を使用するため、心電図の管理をすることは必須でした。
しかし、心電図の解読は本当に難しくて、情けないことにしっかり勉強することから逃げていました。
新人看護師の指導役になり、このままではいけない。正しい指導を行わなくてはと、やる気を出して書店に向かったのですが、手に取る本全てが難しい・・・。
心が折れそうになったところで手にしたのがこちらの本でした。
全ページがカラーで、図が沢山使用されていて、本当に簡単に必要最低限のことだけが記載されています。
基礎中の基礎、PQ、R、STとは?から丁寧に解説してくれています。
心電図が本当に苦手だった私が「これはよくない波形だ!」とベッドサイドに飛んでいけるようになりました。
そこで何を観察して、何を報告したら良いのかを一目でわかるようにまとめてくれているのは本当にありがたいです。
ある程度知識のある人には物足りないと思います。
本当の初心者や心電図アレルギーの人にぜひ読んでもらいたいです。
■からだがみえるシリーズ(1票)
【9/10点】
新人看護師や保健師におすすめ
(Mさん/福岡県/30代前半/女性)
大学卒業後、消化器内科の病棟看護師として勤務したのち、現在は健康コンサルティング企業にて保健師として従事しています。
元々は、正社員で約390万円くらいでしたが、現在はメインで雇用していただいてる企業にてアルバイトとしての年収が約300万円です。
その他、健診業者にて看護師として働いています。
からだがみえるシリーズを勧める大きな理由は、カラー写真が載っており、新人看護師や保健師にとって、理解しやすいからです。
大学生時代の教科書ではわからない、実際の現場で使える知識(必要な研修や看護する上でのポイント等)も記載されています。
また、わかりやすい医療用語を用いているため、看護師や保健師以外のコメディカルにも説明しやすいです。
具体的には、病院や地域での保健指導に従事している管理栄養士に対して、病態の説明をする際に、この書籍を用いると、非常にわかりやすいと好評でした。
シリーズとなっており、調べたい事がある際に、すぐに必要な分野の書籍を手に取ることができることも良いと感じます。
■ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術(1票)
【8/10点】
看護技術に不安のある経験の浅い中途入職者にもおすすめ
(Sさん/東京都/30代前半/女性)
看護師9年目です。
現在は2次救急の中規模病院の内科病棟で5年勤務しています。
正規職員で、3交代勤務。転職経験は2回。血液内科(数か月のみ)→精神科→内科の転職経験があります。
『ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術』は、看護師1年目に向けて看護技術を説明する文献になります。
この文献は絵や漫画が多く、分かりやすいことばで看護技術が解説されています。
精神科から内科へ転職した際、看護技術に不安があったのですが、この文献があればもう少し自信をもって看護に取り組めたのではないかと思っています。
現在この本を読んで、看護技術の再確認が出来ています。
また、知識があいまいであった自分の技術の復習も出来、ありがたい本です。
続編も出ており、続編では、2年目に向けた技術解説本となっています。
看護師1年目に向けての本ですが、基本的な看護技術が記載されているので、経験の浅い中途入職者にも適していると思います。
そのため、他の看護師にも勧めたいと思い、この本を紹介しました。