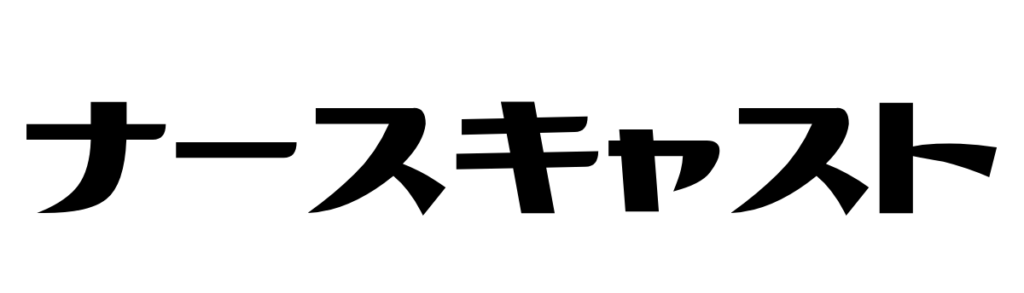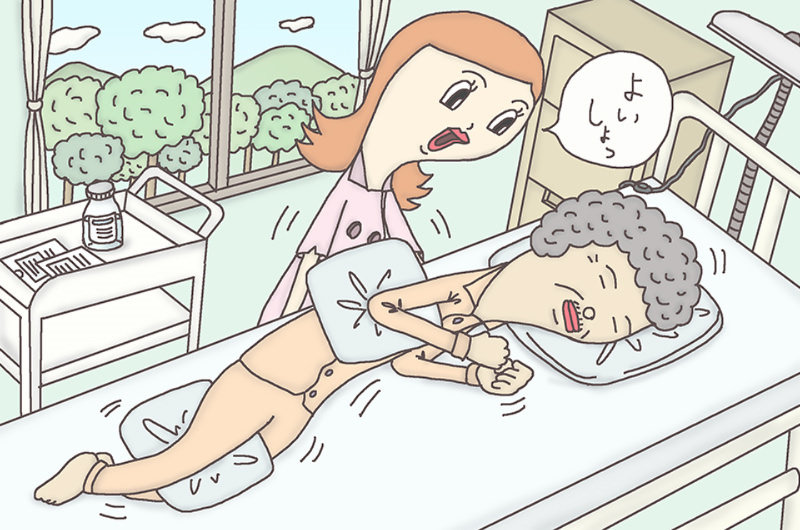認定看護管理者の役割とは
認定看護管理者の資格、役割について詳しく解説しています。
認定看護管理者の役割とは?
・認定看護管理者は目標を達成するための管理、組織作りをするトップマネージメントの役割を担う。
・ファースト~サードレベルの教育課程がある。
・看護師長、看護部長とキャリアアップする人に最適の資格で、シフト表作りは腕の見せ所。
認定看護管理者制度とは?
病院にとって、日標を達成するための組織づくりをするトツプ・マネージメント、の役割を担う看護部長や部門の業務やスタッフを管理し、部署の看護サービスに対して責任と権限をもつ看護師長の役割は非常に大切です。
専門看護師、認定看護師以外に管理の役割を担う看護師のために、日本看護協会の認定する「認定看護管理者」という資格があります。
認定看護師管理者は、スタッフを管理したり、職場環境を変えて、提供する看護サービスの質を保証、改善を進めていく役割を担っています。
日本看護協会では、1992年から人材育成のために教育課程を設けて、認定審査を行っています。
認定看護管理者制度の目的は以下の通りです。
認定看護管理者制度は、多様なヘルスケアニーズを持つ個人、家族及び地域住民に対して、質の高い組織的看護サービスを提供することを目指し、看護管理者の資質と看護の水準の維持及び向上に寄与することにより、保健医療福祉に貢献します。
日本看護協会が
管理者として優れた資質を持ち、創造的に組織を発展させることができる能力を有する
と認めた者です。
認定看護管理者になるには、看護師免許を有し、免許取得後の実務経験が通算で5年以上あることが要件です。認定看護管理者の審査に合格すると「認定看護管理者」として登録されます。合格後は看護管理の実績を報告し、5年ごとに更新審査があります。
2018年12月現在、3772名の認定看護管理者が病院、介護老人保健施設などの副院長・看護部長、訪問看護ステーションの所長などの役職について活躍しています。もちろん資格が無くても看護管理の仕事はできますが、病院によっては看護部長から副院長に登用するときの要件にしているところもあります。
教育課程には、3つの段階があります。第1段階(ファーストレベル)は150時間、第2段階(セカンドレベル)と第3段階(サードレベル)はともに180時間の学習が課せられます。ただし、一定の管理業務の経験を持ち、大学院で管理を学んだ人は、このステップを経ることなく審査を受けることができます。
要件をまとめると以下のいずれかを満たす必要があります。
①認定看護管理者教育課程サードレベルを修了している者。
②看護系大学院において看護管理を専攻し修士号を取得している者で、修士課程修了後の実務経験が3年以上ある者。
③師長以上の職位で管理経験が3年以上ある者で、看護系大学院において看護管理を専攻し修士号を取得している者。
④師長以上の職位で管理経験が3年以上ある者で、大学院において管理に関連する学問領域の修士号を取得している者。
認定看護管理者は、管理的業務に関心があり、管理的業務に従事することを期待されている人がなります。看護師長、看護部長とキャリアアップを目指す人に取ってもらいたい資格です。
看護部長は看護師キャリアの頂点で、病院経営のトップである院長の意思決定に参加します。そして、院長や副院長の補佐を行い、病院の方針を看護部に反映し業務計画を作成する必要があります。
看護師長は一般企業でいう課長に相当します。看護部長だけでなく、医師と看護師の橋渡しの役割を果たします。
マネジメントの神様、ピーター・ドラッカーは「正しい人事のために4時間かけなければ、後で400時間とられる」と言ってます。
シフト表(勤務表)の作成は、腕の見せどころといってよいでしょう。
◎ファーストレベル
【教育目的】
①看護専門職として必要な管理に関する基本的知識、技術、態度を修得する。
②看護を提供するための組織化ならびにその運営の責任の一端を担うために必要な知識、技術、態度を修得する。
③組織的看護サービス提供上の諸問題を客観的に分析するための能力を高める。【教育目標】
①部署の課題を明確にし、目標設定に参画できるようにマネージメントスキルを養う
②論理的思考を理解し、部署課題に取り組む能力を養う
③チーム医療のメンバーとして、連携しながら教育的にかかわれるように視点の拡大を図る
◎セカンドレベル
【教育目的】
①第一線監督者または中間管理者にもとめられる基本的責務を遂行するために必要な知識、技術、態度を修得する。
②施設の理念ならびに看護部門の理念との整合性をはかりながら担当部署の看護目標を設定し、その達成を目指し、看護管理過程が展開できる能力を高める。【教育目標】
①看護部の課題を概念化し、部署に提示する能力を養う
②論理的思考に基づき分析し、部署の課題を解決できる能力を養う
③スタッフのキャリア開発を支援する力を養う
◎サードレベル
【教育目的】
①社会が求めるヘルスケアサービスを提供するために看護の理念を揚げ、それを具現化するために必要な組織を構築し、現場に軸足を置いた運営ができる能力を高める。
②看護事業を起業し、運営できる経営管理能力に関する知識・技術・態度を修得する。【教育目標】
①組織変革を行い、創造的に発展させることのできる能力を養う
②地域の状況に応じヘルスケアシステムを構築できる能力を養う
③保健医療福祉の現状を分析・データー化し、政策提言できる能力を養う
病院は毎日24時間365日、切れ目なく看護を提供するので、昼夜を問わず必ず看護師が出勤しています。
その出勤を管理しているのが「勤務表」です。勤務表は各部署の責任者、「看護師長」により4週間単位で作られています。
この勤務表の作成は基本的に手作業です。
勤務表を作るときには、入院している患者さんの人数や重症度、病棟全体でどんな検査や手術が予定されているのか、会議や病院の行事といったことを考えなければなりません。
また看護師の経験年数、家庭環境、人柄・人間関係を考慮したうえで、勤務の希望を加味して必要な人数を勤務時間帯ごとに配置します。
勤務には「日勤-夜勤」の2交代制と「日勤-準夜-深夜」の3交代制があります。
準夜勤務と深夜勤務を続ける「16時間夜勤」を採用する病院が増えています。
しかし、労働科学の研究者は健康リスクと医療安全の観点からこの長時間勤務に警鐘を鳴らしています。実際に看護協会の「時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」(2008年)から、過労死のハイリスクに当てはまる人が約2万人に上ると報告されています。
勤務表の作成には診療報酬上の要件もあります。診療報酬とは「医療保険サービスの価格」で、医療行為に関する行為、一つ一つに価格が設定されています。
その価格の一覧表が「診療報酬点数表」です。
この診療報酬は全国一律の価格が設定されており、どこかの都道府県だけが手術が安いということはありません。
診療報酬は点数で、表され、1点が10円です。診療報酬は病院の収入源になります。