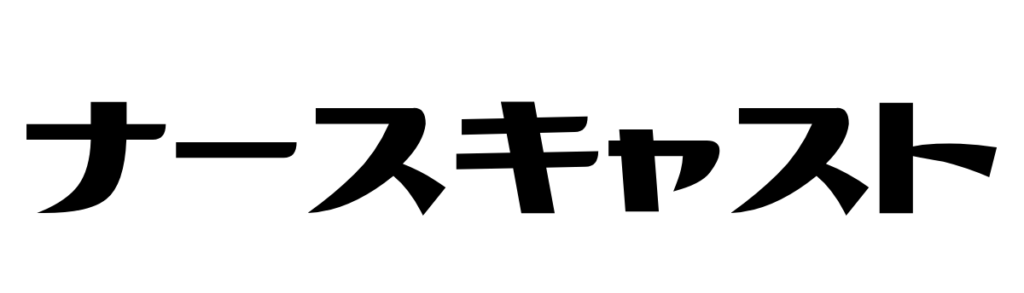看護師の人数と看護師の職場|准看護師・保健師・助産師を含む看護職の仕事とは?
准看護師・保健師・助産師を含む看護職の仕事とは?
看護職には、「看護師」「保健師」「助産師」と「准看護師」の4種類の資格があります。看護師は女性が多く、かつては「看護婦」と呼ばれ、男性の場合、「看護士」と呼んでいました。2001年に「看護師」に統一されました。
看護師、保健師、助産師は、国家試験に合格して厚生労働大臣から免許を得る「国家資格」です。准看護師は、都道府県が行なう地方試験に合格して、都道府県知事から免許を得ます。免許は一度取得すると一生使え、更新制度はありません。
「看護師」「保健師」「助産師」「准看護師」は、『保健師助産師看護師法』(保助看法)が第2次大戦後に制定され、その中で規定されています。看護師とは、厚生労働相の免許を受け、傷病者や産婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを「業」とする者、です。保健師とは、厚労相の免許を受け、保健指導に従事することを「業」とする者、です。
助産師とは、厚労相の免許を受け、助産または妊婦、産婦、新生児の保健指導を「業」とする女子、です。准看護師とは、都道府県知事の免許を受け、医師、歯科医師、看護師の指示を受けて、傷病者や産婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを「業」とする者、となっています。
現在、日本全国で働いている看護職は、約160万人(2014年末、160万3,108人)います。日本の人口1億2,800万人のうち、160万人が看護職についているので、国民の80人に1人は看護職というわけです。ちなみに、医師が約29万(2012年末、30万3,268人)、歯科医師が約10万人(同、10万2,551人)、薬剤師は約28万人(同、28万0,052人)で、全国の警察官も約28万人(2012年総務省による)です。
つまり看護職は、医師と歯科医師と薬剤師と警察官の合計を上回る人数なのです。小学校の教員数は約41万9,000人(平成24年度学校基本調査)ですから、医師、歯科医師、薬剤師、警察官に小学校の先生も加えて、看護職とほぼ同数です。女性の労働人口は2,642万人なので、働いている女性の約5%を占めているのが、看護職です。
保健師については、全体の約7割が市町村、保健所に就業しています。ちなみに保健師は看護師国家試験に合格後、1年以上の保健師養成課程を修了したうえで、保健師国家試験に合格しなければなれません。
助産師は全体の約6割が病院、約2割が診療所に就業しており、助産所に5.5%が就業しています。助産師も看護師の資格を得た後、助産師国家試験に合格しなければなれません。
准看護師は、病院に約4割、診療所に約3割、介護保険施設等に約2割弱が就業しています。准看護師は、50代以上が多く、20代、30代が少ないのが特徴です。看護師、保健師、助産師が少しずつ増えているのに対し、毎年微減しており、現在では約35万人になっています。
男性の看護師は約6万人が登録されています。男性の看護師の割合は2012年時点で全体の約6%ですが、年々増加しています。病院では男性看護師の需要は高まっており、積極的に男性看護師を雇用する施設も増えています。男性看護師の93.2%は、病院・診療所で働いています。特に精神科、手術室、ICU・救命救急のニーズは高いです。その理由として、男性の体力を活かせる場面が多いからだといわれています。
看護師の就業場所として一番多いのが、病院(62%)で、次が診療所(21%)です。つまり、看護師の8割以上が医療機関で働いていることになります。最近では看護師の活躍の場は拡大しており、介護老人保健施設に4万人、訪問看護ステーションに3万人、介護老人福祉施設に3.2万人が働いています。
そのほかには、事業所、学校、研究機関、工場、保健所、市町村役場、助産所、社会福祉施設、居宅サービス業など様々な場所で看護師が活躍しています。今後は、在宅医療が広がっていくので、訪問看護師をいかに増やしていくかが検討されています。
2014年度診療報酬改定では、7対1病床の資格条件が厳格化されました。そのため、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年度を目指し、医療構造が大転換し、看護師の働き先も大きく変わります。急性期病院では看護師のニーズは減り、介護施設、地域包括ケア病棟・回復期病棟、長期療養病棟、訪問看護ステーションでは看護師の活躍の場が増えると考えられています。
看護師の職場と仕事の特徴をざっくりまとめると以下のようになります。
病院・クリニックは治療の介助・処置、入院患者の療養のお世話、外来での相談、訪問介護、分娩介護ほか部署と職種によってさまざまです。
訪問看護ステーションは在宅療養する患者をすべて対象にしており、幅広い知識が必要とされます。
老人保健施設では、介護職と共に働き、医療の専門家の一人として高齢者の介護問題を担当します。
企業・保育所では、組織にいる人の健康を維持するように努めます。
現在、病院看護師はおよそ75万人、診療所に13万人、介護施設に6万人、訪問看護ステーションに3万人いますが、医療コンサルティング会社のグローバルヘルスコンサルティング・ジャパンによると病院看護師は2025年までに14万人減少すると分析しています。今後、国の改革シナリオによると、現在150万人ほどの看護職員数は、2025年度までに195~205万人必要です。
なおオランダ並みの在宅看護を実現するには、その時までに訪問看護師が17万人必要とされ、14万人増やす必要があります。70万人以上いる潜在看護師の復職や新設ラッシュが続く看護学校の卒業生が、在宅看護の即戦力として期待されています。
看護師の人数と看護師の職場まとめ
看護職は女性の就業者の約5%を占め約160万人いる。医師、歯科医師、薬剤師、警察官、小学校の先生を合わせた人数と看護職はほぼ同数。
看護師の職場は病院(62%)と診療所・クリニック(21%)で約8割を占める。残りは事業所、学校、研究機関、工場、保健所、市町村役場、助産所、社会福祉施設、居宅サービス業などさまざま。
看護師に必要とされるもの
看護師は、医師の治療を支えながら患者さんの療養生活を支えます。
患者さんの変化に少しでも早く気付くことができるように、いつもたくさんの視点から患者さんを見て対応しています。
看護師の仕事場は医療施設ですが、医療施設には大きくわけて「診療所」と「病院」の2種類があります。
患者さんの状態によって両者が連携をしながら、医療サービスを提供しています。
診療所とは、入院設備をもたない、またはベッド数が19床以下の医療施設のことです。
通院してくる患者さんの診察が中心で、状態の安定した病気や、日常的な病気をおもに扱います。
専門的な治療が必要かどうかを判断することも診療所の大切な仕事です。
看護師は、ケガや病気の処置だけでなく患者さんやその家族とのコミニケーションがとても重要です。
コミニケーション能力は、看護師の基本とも言えます。
温かい言葉がけや、さりげない心配りも大切です。
仕事をしていくなかでコミニケーション能力は上がっていきますが、求められるのは技術だけでなく温かい人間性と体力です。
患者さんの車いすへの移乗であったり、入浴の介助など、体力が必要とされる作業があります。
夜勤勤務があるなかで力仕事もあるので、睡眠も不規則になることもあり、体力が必要になります。
大事なのは、看護師の仕事を好きであり続ける気持ちを持つことだと思います。
そういう気持ちを持つためには、つらいことがあってもくじけずに立ち向かっていくことも必要になると思います。
看護師になって感じたこと
ナースという言葉に惹かれて看護師になりました。あの頃は白衣の天使と言われる看護師の仕事って素敵だなという気持ちでいっぱいでしたが、いざ看護師の仕事を始めると体力がついていかなくて毎日ぐったりしていました。
働いて初めて、すごく体力のいる仕事だということを知りました。しかも新人看護師だった頃は、先輩に怒られたり嫌味を言われたりなどもして本当に辛かったです。
仕事に慣れてきて仕事で失敗をしなくなると、だんだん怒られなくなってきたのでほっとしましたが、責任が重くなってきました。
看護師になってからは毎日疲れているような気がします。休日はごろごろして外で楽しくショッピングや映画を観たりなどできなくなりました。
でも看護師仲間で集まった時に、みんな私と同じように悩んでいることがわかってからは少しスッキリとして働けるようになったんですよね。
サービス残業が多い職場だとすごく辛いのですが、今は転職してサービス残業があまりなくなったので楽になりました。
転職してからはお給料が減りましたが、身体が楽になったので笑顔で仕事をすることができるようになったんですよね。
看護師がクタクタになるまで仕事をしたらだめだと思うんです。ミスが増えますし、心から患者さんのお世話をすることができなくなると思います。
あまり稼げなくても良いから、精神的にも肉体的にも余裕のあるぐらいの仕事量が理想ですね。そうすれば質の高い仕事をすることができると思います。
看護師のよくある悩みと対処法
看護師は人の命を預かる仕事として、責任も遣り甲斐もある職業です。医師不足に伴って、より専門知識のある看護師が求められていますし、高齢化社会の日本では看護師の需要はますます高まるばかりです。手に職をつけたいと看護師を目指す人も増えてきているようです。
体力的にも精神的にもとても大変な仕事であることから、よく聞かれるのが仕事がハードで、人を相手としていることから神経を使い、少し間違えば患者を命の危険にさらしてしまうと気が抜けないという悩みです。
一時も気を緩めることなく、過労働で残業も多い、大きな病院なら夜勤だってあるし、2交代制なら勤務時間も長い、となると体力的にも精神的にも大変なことがわかります。
その対策としては、やはり自分の生活スタイルに合った職場を見つけることです。看護師の活躍の場はたくさんあり、訪問看護や介護施設、個人クリニックなどがあります。
例えば訪問看護なら、在宅で医療措置を必要としている方のお宅に訪問してケアを行います。自分のペースで働けて、人間関係に悩むこともありません。でも、まわりに頼れる人がいないので責任は全て自分です。
介護施設の看護師の仕事は、入居者の体調管理や医療措置、薬の準備などで、時には介護士としての業務をすることもあります。夜勤はなく、オンコール体制の場合が多いので、なにかあれば夜間でも駆けつけることもあります。
クリニックでは医師の診察や治療の補助、受付や書類の整理、雑用までこなすことが多いようです。クリニックでは夜勤もありませんし、土日は休みなのがメリットです。
でも、職員が少ないので、人間関係に気を付けないと仕事がしづらいことになります。職場によって給料や勤務体制は大きく変わってくるので、しっかり見極めて就職することをオススメします。
看護師の職場と転職について
看護師の職場といったら、病院を連想される方も多いのですが、近年では様々な分野にて看護師の力が必要とされており、看護師の転職は他職種に比べると比較的簡単かもしれません。
看護師の人材不足が近年大きな問題となっていますが、その背景には看護師の需要が高まっていることが挙げられます。
高齢化社会となり、病院の数も増えて、その分人材が必要とされます。それに加えて福祉施設の数も増えているのですが、実は福祉施設にも看護師が必要です。
他にも、病児保育など様々な分野にて看護師配置が義務付けられており、病院以外にも多くの施設などが看護師の人材不足に悩まされています。
そのため、看護師の転職は選択肢が広いといえ、夜勤などの勤務に入るのが難しい場合は、病院でも入院施設が備わっていない病院を選ぶことで日勤のみの勤務が可能となっていますし、福祉施設なども基本は看護師の夜勤はあり得ないため、それらを選択されることがおすすめです。
また、なかには夜勤に入って稼ぎたいといった方も多いと思いますが、そのような場合には、最近では夜勤専門の看護師求人も多いので、シフト制ではなく、夜勤だけの勤務も可能となっています。
近年では、看護師の人材不足を解消するために、夜勤だけといった勤務や日勤のみなど、勤務時間を固定する病院も増えています。
看護師の転職は病院だけに目を向けることなく、福祉施設や病児保育なども看護師の力を求めているということを念頭に入れると、転職先の幅が一気に広がります。
看護師の幅広い活躍の場
看護師の職場で、まず思い浮かぶのは病院や医院ですが、この他にも見落としがちな職場があります。それは老人施設や、特に大きな会社にある医務室です。
病院や医院のように、患者さんの対応をひっきりなしにすることはないので、あまりバタバタとした職場や忙しすぎる環境を好まない人には向いているかも知れません。
老人施設も、アパート型の住居としている所や、デイサービスやデイケアやリハビリ施設と言う風に、そのタイプはたくさんあります。そう言った場所に看護師は在中して、利用者の健康管理やサポートをするのも看護師の仕事です。
もちろん、全ての老人施設に看護師がいるとは限りませんが、そう言う職場の狙い目もあるので、ぜひ検討されるのも良いと思います。
そして、もう1つは会社の医務室ですが、大企業には比較的ある所が多いと思います。社員数が多ければ、それだけ企業全体として社員の健康管理を行わなくてはなりません。
定期的な健康診断を始めとして、普段の社員の体調を観察して行くことも重要な役割です。医師も在中していれば、社員が体調を崩した時の見守りだったり、診察のお手伝いや場合によっては血液を採取したり点滴注射をすることもあります。
また、秋から冬にかけてインフルエンザの集団感染を予防するために注射を行ったりして行きます。この会社の医務室の場合でも、毎日忙しいこともあまりないと思いますので、やはり老人施設と同様に看護師にとっては穴場かも知れません。
本来の看護師の業務とは違った仕事
看護師の仕事は診察に来た患者さんの対応だけをしているのではなくて、時には保育士のような幼稚園ような仕事をすることもあります。
例えばお母さんが診察をするために来院して小さな子供さんがいた場合、赤ちゃんだったら看護師が抱っこをしてあげます。
絵本が分かる年齢であれば待合室で読み聞かせをしたりして、お母さんの診察が終わるまで面倒を見ている場合があったりします。
そして患者さんが途切れた時には、診察や治療で使う物を在庫が切れないように下準備をしています。
反物のようになっているガーゼを、はさみで様々なサイズに切って必要に応じて折ったり、患者さんに軟膏を付けるために渡す綿棒を、真空にするような機械で3本位にまとめてパックのようにしておきます。
さらに綿球と言って耳鼻科等の治療や処置でよく使われていますが、綿を丸めてから先程と同じように真空にして雑菌が入らないようにします。
これだけでも、看護師って結構細かくて地味な作業をするなと思ってしまいますが、患者さんの診察の時に撮影したレントゲンの整理整頓や、時には医師がレントゲンを撮影した物を現像していたこともありました。
他には患者さんを気持ち良く迎え入れるために、玄関や庭や待合室にトイレ掃除まで、直接看護師の業務とは違ったことまで担当します。
保健師とは?
保健師は、子どもからお年寄りまで対象も多岐にわたり、専門職として科学的な知識と技術で的確に判断を下さなければいけない場面がたくさんあります。
同じ職業の人だけでなく、いろいろな職種の専門家とチームを組んで仕事をしなければなりません。
あらゆる健康レベルの人たちと接する職業なので、保健師が健康で心にゆとりがなければなりません。
保健師は、さまざまな価値観をもつ人たちと関わっていき、その人たちの考えや生活を尊重しながら、どのようにしたら、相手の人がより健康な生活が送れるのか、考えて支えるのが保健師です。
自分の価値観を押し付けるのではなく、相手の価値観も受けいれられる柔軟な思考と人間性が重要になってきます。
地域の人たちがどのような生活をしていけば、より健康な生活が送れるのか、理論に基づいた科学的裏づけをもって判断できることが大切です。
保健師は、地域の人たちがその人らしく生きていくためには、どのような支援が必要なのかを客観的に見極めることが求められます。
経年的データの分析から、年齢や地域の特徴等を考慮して今後起こりうる疾患等を予測する力も必要です。
ですので、新しい情報を常に取り入れていかないと、時代のニーズに追いついていけないのが保健師の仕事といえます。
また、医療系などのチームを組んでいろいろな人たちと協力し合って、仕事をしていく場面が数多く存在するので、チームで知恵を出しあって努力することが大切です。
助産師とは?
助産師の主な仕事は、妊婦さんに元気でいてもらうこと、そして赤ちゃんの誕生をお手伝いすることが助産師の仕事です。
助産師が女性同士の立場で妊婦さんを支えながら、妊婦さんと出産に向けて共に考えていきます。
妊婦健診では、出産のために大切なことを妊婦さんに伝えながら、ふだんの何気ないことを話しあったりもします。
妊婦さんの身近な存在になることで、ちょっとしたことでも相談できるような関係を築くことができます。
助産院では、天敵や帝王切開などの医療の力が必要となった場合、産婦人科へ妊婦さんの搬送をお願いすることがあります。
出産のときは、妊婦の状態が正常な場合は助産師として助産行為を行い、異常があるさいは医師との協働、または補助を行います。
産後は新生児のケアを行い、こうした活動は有床または無床の助産所を開設し、地域で助産師として開業することができます。
助産師の多くは病院や診療所で働いていますが、最近は院内助産所や産後ケアという働く場もあります。
また、助産師の仕事は幅広く、母子保健センターや、行政関連の仕事をする助産師もなかにはいます。
助産師は、単に分娩介助をするだけではなく、思春期の児童、または生徒から子育て中の女性とその子どもに至るまでの健康を幅広く支援する仕事も行っています。
助産師は、妊婦さんと赤ちゃんの命を守りながら、社会での生活を支援するために、社会福祉や教育などさまざまな分野の人たちと連携をしながら働いていきます。
看護師として大切なこととは
私が以前勤めていた病院は、大阪の中心地から少し外れたやや治安の悪い地域にありました。
総合病院で色々な病気を患った患者さんが来られていました。私の働いていた病棟もがん末期の方や手術前後の方、眼科の病気など年齢層も様々な患者さんがおられました。
看護学校を卒業したばかりであまり人との対話経験も少なかった私は、看護師の専門技術よりも人とのコミュニケーションに困る毎日でした。
ある日いつものように糖尿病を患った50代男性患者さんの血糖検査にうかがいました。血糖を測りましょうか、と声をかけると『いやや』と私をにらみつけました。何度かお願いしましたが断固として測らせてはくれませんでした。
患者さんが拒否するから検査できないという理由は通用しません。どうしていいかわからない中、途方にくれる私がいっしょうけんめい話しかけているうちに自然と世間話になりました。
その方が病気になってどんな辛い思いをしているのか、毎日何度も受ける血糖の検査の痛みさえも受け入れられなくなっていることなどを話し出したのです。その時、私はただしなければならない作業をこなすように仕事をしていたことに初めて気付きました。
看護師になって初めて患者さんの気持ちに気付き、寄り添うことが出来ました。気付けば患者さんの表情も穏やかになり『困らせて悪かったな』といいながらすんなり血糖測定をさせてくれました。
その日から私の中で仕事に対する姿勢が変わった気がします。あれから10年以上が経ちました。
正直、仕事量も多くて時間に追われる毎日ですが、あの時の経験が私の看護師としての仕事に対する基本になっているような気がします。今でも一つ一つルーチンでこなすのではなく一人一人患者さんの立場にたって対応するように心がけています。
看護師の本当に必要な考え方とは?
看護師経験の浅い私の考えたまとめになります。
ナースは勤勉な仕事だと言われますが実はそのようなことな無く、学生まで勤勉に学問に取り組んでおけば働いたとたんほとんどの人が羽目を外したくらい適当に仕事をこなしています。
専門性を高めるために、専門看護師や認定看護師の資格をとったり、診療情報管理士などダブルライセンスの取得を目指す看護師は多いのが現状ですがそれはあくまで資格取得のための勉強であり、仕事に勤勉になるナースにはつながりません。
一方、経営参画を期待して看護師を副院長に採用する病院が増えるなど、病院内でも多種多様な仕事内容を求められる役割は大きく変化していますのでそういった癒着などが原因になります。
ここで期待されているのは、看護師としての知識の深さや広さだけでなく、看護師視点での現場に対する改善活動や経営貢献が重要になります。
いくら勤勉に仕事をこなしてもここの部分が欠けてしますと評価されないのが現実です。
つまり、既存知識の提供に終始せず、看護の専門性を活かし、困難な状況下における思考力、判断力のあるリーダーシップを発揮できる人こそ真のナースになることができるのです。
しかし多くの看護師は、これを苦手としています。なぜなら、中堅の看護師が困難事例にぶっかった場合、どのような行動をとるかというと”先輩や同僚と話し合い、出た意見を自分なりにまとめて解決策を考えるが、うまくいかなければ仕方がないと諦める。といった思考になるのです。
このような思考や行動から、発生した解決困難な問題に対する看護師の思考パターンが理解できました。