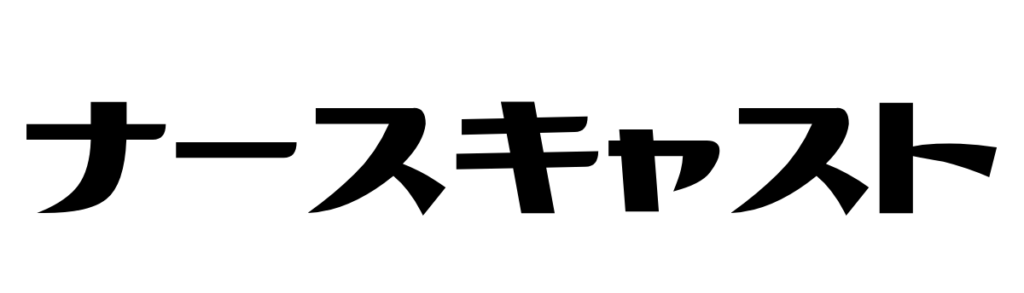専門看護師と認定看護師の違い
看護職として法律に基づいて、免許が与えられる職種として、看護師、准看護師、保健師、助産師があります。2006年以降は、保健師と助産師は看護師国家試験に合格していることが要件になり、現在は保健師と助産師は看護師であることが前提です。
こうした免許が必要な看護資格以外に、公益社団法人日本看護協会が認定する看護資格があります。それが、『専門看護師』と『認定看護師』です。
専門看護師、認定看護師ともに実務経験が5年以上(うちそれぞれの分野で3年以上)が必要です。免許の更新はどちらも5年毎に行われます。
更新については、看護実践の実績や研修実績、研究業績等の書類審査がありますので、取得後、臨床の場から離れていると更新が難しくなります。
資格を取得するうえでの大きな違いは、専門看護師が日本看護系大学協議会指定の大学院を修了しなければいけないのに対し、認定看護師は日本看護協会指定の教育機関で教育を受け、認定試験に合格することが条件であるということです。
そういった意味では、実務経験以外に、2年かけて教育課程を修了しなければならない専門看護師の方がハードルがやや高いといえます。
いずれにせよ、資格を取れば、高度な医療技術を持つ医療機関に転職したり、昇進や給与・手当が増える可能性は高くなります。
キャリアアップを考えている方は、専門看護師や認定看護師などの資格に挑戦してみるのもよいでしょう。
◎専門看護師とは
まず専門看護師は、特定の専門看護分野に関して、看護系大学院で学び、資格審査に合格した看護師です。現在、全国におよそ1,883人が活躍しています。特定されている専門看護分野は、11分野で(2016年12月末時点)、それぞれの場において、さまざまな役割を果たすことを目的に活動しています。
11分野は「がん看護」、「精神看護」、「地域看護」、「老人看護」、「小児看護」、「母性看護」、「慢性疾患看護」、「急性・重症患者看護」、「感染症看護」、「家族支援」、「在宅看護」です。実際の臨床現場では、頭文字をとって「CNS(しーえぬえす)」と呼ばれています。
専門看護師の目的は以下の通りです。
複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、特定の専門看護分野の知識及び技術を深め、保健医療福祉の発展に貢献し、併せて看護学の向上をはかる。
専門看護師には、以下の6つの役割があります。
①専門分野において卓越した看護を実践する(実践)
②看護者やケア提供者にコンサルテーションを行なう(相談)
③必要なケアが円滑に行なわれるために、保健医療福祉に携わる人々のコーディネーションを行なう(調整)
④倫理的な問題や葛藤の解決を図る(倫理調整)
⑤看護者に教育的役割を果たす(教育)
⑥専門知識・技術向上や開発を図るため研究活動を行なう(研究)、です。
たとえば、がん看護CNSの場合、患者と共に治療方法を選択し、日常生活での影響を説明し、患者さんの暗くなりがちな気持ちに耳を傾けます。主治医とうまくいかないという悩みを持った患者さんの立場に立って、担当を変えてもらうなどの役割を果たすこともあります。
この専門看護師の資格を得るためには、質の高い看護ケアの提供を可能にする深い知識と技術を持つことが必要です。
専門看護師の資格認定は日本看護協会が年に1回行なっており、試験を受けるためには、専門看護分野での実務経験を5年(うち3年以上は専門看護分野の実務)以上積んでいること、看護系の大学院を修了して所定の単位を取得していることが必須条件になります。
勤務施設は病院が最も多く、1585人(84.2%)で、次に大学・学校が153人(8.1%)、そして訪問看護ステーションが42人(2.2%)となっています。
また認定看護師の制度制定時、わずか12校だった専門看護師を育成する看護系大学院の数が2016年には288校まで増加しました。
認定看護師の人数も2018年には、21分野19,835人に増えました。
専門看護師へのキャリアアップは5年目から?
転職時、多くの看護師が悩んでいるがキャリアアップです。
どの時期からキャリアアップを検討するべきであるのか、というのはかなり難しいことではあるのですが、基本的にはまずは5年程度から、となるでしょう。
5年目まではまだまだどうしても一人前を目指すべきである、ということになるからです。
どうして5年以上からなのか、といいますとそうしますと専門看護師というのを認定試験として受けられるようになる可能性があるからです。
専門看護師は、5年以上の実践経験と看護系大学院での修士課程修了の2条件をクリアした看護師が、ということになっています。
ですから、決して条件が緩いわけではないのですが、とりあえずキャリアアップしたい、より能力が高い看護師を目指したい、という人にはこの資格を目指すことがお勧めできるようになります。
6つの役割があり、13の看護分野にわかれていますから、かなり大変ではあるのですが、とにかくこの資格があればまずは評価されることでしょう。
正看護師であればこうした資格を追加で取得できるように目指すとよいでしょう。
当たり前ですが准看護師の場合は正看護師を目指す、ということになります。
しかし、給料形態がリセットされてしまうことがありますから、正看護師を目指すということからするとよいでしょう。
看護師のキャリアといっても目指すのは人によって違うのです。
◎認定看護師とは
認定看護師の目的は以下の通りです。
特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて、水準の高い看護実践ができ、看護現場における看護ケアの広がりと質の向上をはかる。
認定看護師(略称=CN)は、看護現場において以下の3つの役割が期待されています。
①個人、家族および集団に対して、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護を実践する(実践)
②看護実践を通じて看護職に指導を行なう(指導)
③看護職に対しコンサルテーションを行なう(相談)
認定看護師になるには、5年以上の臨床経験を経たうえで、6か月、600時間の教育を受け、認定試験に合格することが条件になります。つまり、半年間職場を離れることになります。また5年ごとに看護実践や、自己研鑽の実績をまとめて、資格の更新審査を受ける必要もあります。
看護分野は専門看護師と比較すると限定的で、21分野あります。
それが、「緊急看護」、「皮膚・排泄ケア」、「集中ケア」、「緩和ケア」、「がん化学療法看護」、「がん性疼痛看護」、「訪問看護」、「感染管理」、「糖尿病看護」、「不妊症看護」、「新生児集中ケア」、「透析看護」、「手術看護」、「乳がん看護」、「摂食・嚥下障害看護」、「小児緊急看護」、「認知症看護」、「脳卒中リハビリテーション看護」、「慢性呼吸器疾患看護」、「がん放射線療法看護」、「慢性心不全看護」です。
認定看護師は、2017年時点で全国でおよそ1万8728人が認定分野で複雑な治療を行う患者さんに対して、助言をしています。全体の63.9%は資格取得後の勤務条件や給与待遇に変化はない(2012年調査)ということですが、手当がついたり、職位が上がり、昇給したという報告もあります。
勤務場所は、病院が最も多く90%、訪問看護ステーション3.4%、クリニック・診療所1.3%と続きます。
認定看護師として働く為の転職とその条件
転職には様々な目的がありますが、その1つはキャリア形成です。認定看護師などはその1つです。
看護師という職業は、様々なランクが存在します。キャリアによって、そのランクも大別される訳です。
高い技術を保有している方々の場合は、認定看護師というランクになります。一定以上のキャリアがある上に、高い看護技術がなければ、認定されません。
看護師によっては、現在の職場では限界を感じている事もあります。現在の職場ではスキルを伸ばせるレベルも限られますから、転職をする選択肢も浮上する訳です。病院によっては、学べる看護スキルに限界があるからです。
実際、それが正解な事も多いです。現在の職場を退職し、認定看護師として働く為に転職する選択肢が浮上する事もあります。
それで認定される条件として、まず実務経験が1つのポイントになります。実務研修を5年以上受けていなければ、認定されません。ですからキャリアが浅い段階では、認定は難しいです。
そして一番のポイントは、集中講義です。その講義を、半年以上は受講しなければなりません。
あくまでも所定の機関にて講義を受ける必要がある上に、昼間の時間帯に限定されるのです。ですから働きながら集中講義を受けるのは、職場によっては難しい事もあります。
もちろん「全て」の職場にて、講義受講が難しいとは限りません。休職などの手続きを踏めば、受講できる事はあります。基本的には現在の職場の上司の方々と相談する事になるでしょう。